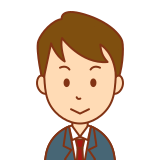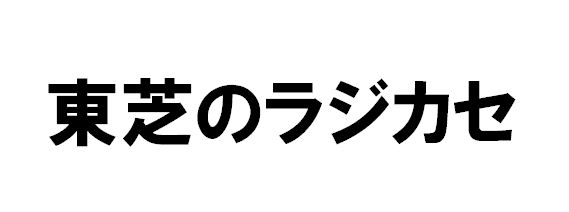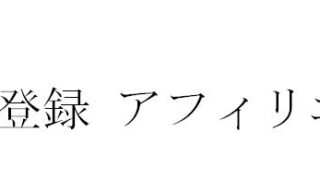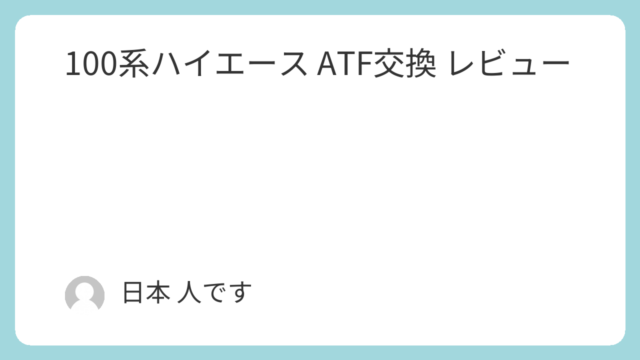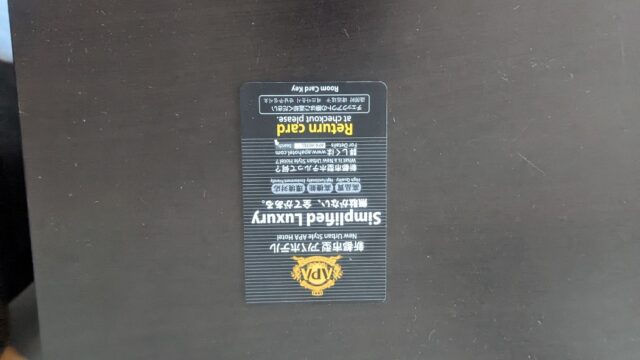どうもデス。
今日は自分で疑問を持ったことをそのままタイトルにw
「残暑見舞いはいつまでに出すのか?」
シンプルのこのテーマで書いていきます。
有名なご挨拶ソフト「筆ぐるめ」さんのサイトによりますと、「立秋」から9月の上旬の頃までに残暑見舞いを出すのが一般的な事とありました。
今現在は2021年ですが、この年の立秋は8月7日でした。関係ないですが土曜日です。
ですので、8月7日から9月8日位までに残暑見舞いが相手に届くように出すと常識の範囲内という事になります。
もう一度、答えをまとめると、「立秋」から「9月の上旬」ごろまでに出すのが正解と言ってよいかと思います。
個々からは、個人ブログの強みともいえる?w勝手に書いて勝手にやりますwww
答えが分かって次にやることがある方はここで次へどうぞ!
暑中見舞いとの関連
残暑見舞いは、暑中見舞いの関連語句の様なものの様です。もともと、スマホなんて無かった時代に(車も無いような)、厚い中元気に過ごしている?と、様子を見にいったりするのが暑中見舞いって感じ。遠方の方には手紙を出したり。その名残が現在も少なからず残る日本独自の文化って気がします。
所で、その時代の手紙は郵便局的な存在が無いわけで、どうやって手紙を届けてたんだろう?今回はそう思い「江戸時代 手紙 配達」と検索をしてみました。すると、当時は結構送料も高額で、いわゆるセレブ層しか頻繁に何回も手紙を出すなんて無理だったみたいです。しかも、ある程度の運賃を渡して依頼、その3日後にやっと相手の元へ手紙が届けられるというもの。
現在では、メールも出し放題で仕事にも多様されていますし、手紙文化もだんだん薄れてきている気がします。そう考えると、日本のオリジナル文化もだんだん薄れてきているという気がしてきます。
ともかく、残中見舞いと残暑見舞いは現在ではほぼ同義語に近い存在の様です。郵政さんの元人気商品「かもめ~る」はこの時期のシーズン商品だったけど、時代の流れで今は無くなったサービスの一つです。
暑中見舞いと残暑見舞いの違いとは
残暑見舞いと暑中見舞いのことについて深掘りするのは今回はここまでにします。
でも気になるのが、残暑見舞いと、暑中見舞いのニュアンスの違いについてです。Google検索で暑中見舞いと検索すると、残暑見舞いと出てきてもおかしくないくらいの微差だとは思いますがw
暑中見舞いは、歴としたルーツのあるものの様です。梅雨以降の立秋以降とするものや、夏の土用(立秋前18日)とする説など。きっと、当時の日本は県それぞれが国の様になっていて、住民みんなが割と顔見知りで、隣の村とかの人も顔も知りだらけ、だったんじゃないかなと感じています。だから、方言とか郷土料理・郷土文化もだいぶバリエーション豊かだったりするって感じで。
最後に
手紙を書くって、メールを書く時とはまた違う相手を想像し、慈しむ気がしませんか?
という事は、遠く離れた家族や兄弟に手紙を綴るのは、もしかしたら素敵な事かもしれないですね。